開催概要
|
日時: |
2022年11月3日(祝) 13:00-17:00 |
|
場所: |
情報セキュリティ大学院大学東京オフィス |
|
参加人数: |
熟議参加生徒 14人
|
参加校: |
北海道石狩南高等学校
|
高校生、教員、企業関係者など69名の参加者を得て、“デジタル社会における学び方と学びの場 オンライン環境で「出来ること」「すべきこと」”をテーマに高校生が3グループに分かれて活発な議論と発表を行いました。
開会の挨拶
司会進行・主旨説明 実行委員長 米田謙三 様
高校生ICT Conferenceの概要及び大まかな流れ、本日のポイントや主旨などを説明しました。地域開催はリアルとオンラインがほぼ半々となり、サミットはリアル開催で実施できたが、感染対策から会場参観者が限定となり、多くの方にオンライン参観をお願いしたことについてお詫びがあり、改めて感謝の言葉がありました。
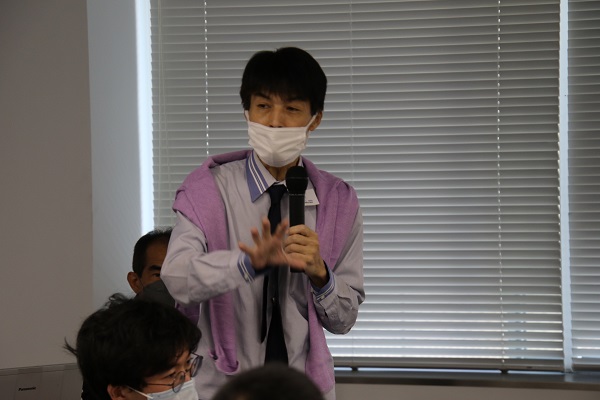
ご来賓挨拶
総務省 情報流通行政局 情報流通振興課 課長 田邊 光男 様
オンラインの発達により、コロナ禍で行動が制限される中でも、物資の調達や授業の受講など、オンラインを活用することにより日常生活を送ることができる。さらには、オンラインを使いこなすことで日常生活のレベルを上げることも可能となった。一方で、オンライン上の情報には様々な情報が流れている。その様々な情報の本質を見極めるための「批判的精神」も必要である。今日の議論を通じ、社会で起きていることを自分事として捉え、社会に対して対峙する力を培って欲しい。

内閣府 政策統括官付 青少年環境整備担当 参事官 鈴木 達也 様
内閣府は、いわば総理大臣直轄の機関として、他の省庁で出来ないところを担当し、カバーしている。私が警察庁にいた2003年にいわゆる出会い系サイト規制法が制定され、内閣府でもネットが青少年にとって危ないものにならないようにという観点で取り組んできた。一方、ネットは正しく活用すれば豊かな世界が広がっていく。みなさんは、デジタルネイティブ世代で違和感なくネットを活用している。今日は、ネットの良い面を活かすという方向で、活発な議論をして欲しい。

文部科学省 総合教育政策局 男女共同参画共生社会学習・安全課
安全教育推進室 室長 西條 英吾 様
毎年、高校生ICTカンファレンスで、生徒の皆さんが集まり熟議をし、提言をいただくことは大変有意義なものだと捉えている。今年のテーマにあるとおり、社会は新しいコミュニケーションの世界に入ってきており、これを踏まえ今年から高校においては情報Ⅰをすべての生徒が学ぶこととなった。今日は、高校生として、進歩するICTを安心安全に、また、主体的に活用する社会とするための議論となることを期待している。

経済産業省 商務情報政策局 情報経済課 企画官 橘 均憲 様
経済産業省の業務の一つに、AIに関してイノベーション促進と倫理的課題の均衡点を探ることがある。AIシステムは使い方によっては人間社会を良くすることができる力を持っており、それを考えるには柔軟な思考が必要となる。一方、例えば学習させるデータに偏りがあると倫理的に問題があるような極端な判断をすることもある。このようにメリット・デメリットの両面を理解し、さまざまな観点から検討し分析していく必要がある。今回のテーマの『出来ることとすべきこと』についても、同様に柔軟な思考とさまざまな観点からの分析によって素晴らしいアイデアを出して欲しい。
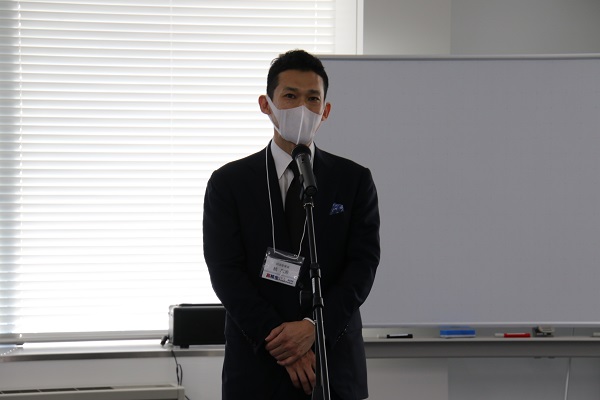
警察庁生活安全局人身安全・少年課 課長補佐 須藤 浩司 様
警察の役割は、犯罪者の検挙と犯罪の未然防止を両輪としている。ネットについては利便性と危険性の両面があり、後者の面ではフェイクが平然と入り込み、利用者は犯罪に巻き込まれる恐れがある。警察庁では予防するための広報啓発やサプライヤーである事業者と連携した対策を講じている。今日は、ネットの課題について様々な課題を多面的に議論し、特に危険性を自分事として捉え、適正な活用方法について活きた知識を身に付けるプロセスとなるよう、この機会を大切にして欲しい。

第一部:
各開催地域代表生徒の自己紹介、地域の取り組みの簡単な紹介(各3分)
第二部:熟議
デジタル社会における学び方と学びの場
-オンライン環境で「出来ること」「すべきこと」
最初はファシリテーターの進行のもと、高校生熟議を開始しました。まずは「学校とは何か」「オンラインのメリットとデメリット」次に「理想のオンライン」「高校生が期待するコミュニケーションの未来」ということを中心にGoogleスライドを活用しながら意見を整理分類しまとめて行きました。具体的な使い方については、テーマにしぼった班や少し大きなテーマで取り組んだ班などいろいろとありました。熟議の中で分からない事は、企業の方や先生方にも随時サポーターとして入っていただき、すばやく答えてくださいました。今回、ファシリテーターはOBOGの大学生が中心となってくれました。事前にオンラインでのフォームやまとめ方を打ち合わせして、滞りなくまとめることができました。(ファシリテーター研修を今年は隔週土曜日3か月間にわたって実施しました。)
★今回のポイント
1.学校とは何か
2,オンラインのメリットとデメリット
3,理想のオンライン
4,高校生が期待するコミュニケーションの未来
(詳細は別紙「熟議録」をご参照ください)
第三部:グループ発表
各グループともプレゼンテーションソフト(Googleスライド)を活用して4分の発表を行いました。(詳細は別紙「グループ発表資料」をご参照ください)
★参考:講評で米田実行委員長がまとめた各班のポイントから
【1班】学校用ポータルアプリの制作
●オンラインツール多くが複雑
●ネット環境が不十分
オンライン授業を受ける事が出来ない。
〇提言
オンライン環境の整備&向上
メタバース・VRの活用 (※環境と金銭)
ポータルアプリの開発(具体的に提示)
【2班】 ICTの技術の差をなくすためのWS
ーインターネット問題を各々の方法で解決するー
ICT技術の差 インターネットリテラシー 興味分野の探求
協働的な学び オープンな環境
〇提言
培った能力でインターネット問題解決に取り組めるWS開催 (趣味ベース)
〇お願い
ICT能力の高い人たちを集めたい 例 ITパスポート取得者
各学校でのアンケートフォームを利用する環境整備
学校での時間の確保
【3班】 高校生が活躍する学びの場と世界共通のコミュニケーションアプリ
・そもそも学校とは
生きるため⇒知識等 コミュニケーション⇒社会性 自己実現
〇提言
高校生が作成する情報科目のマニュアル
タブレットの貸出無料化 経済的支援 平等な学習
生徒同士の教えあい ※代表者が年に四回、オンラインで話し合いマニュアル〇作成
世界共通のコミュニケーションアプリ
世界との密接なコミュニケーション 英語力向上
留学生や外国人労働者などの母校 その県の姉妹高校ともつながる
講評:大阪私学教育情報化研究会 副会長 米田謙三 様
今回初の大学生中心のファシリテーターのもと本当にいろいろな意見がここまで出てきて大変良かった。来年はさらに参加校も増える予定ですのでさらに盛り上げて欲しい。また 今回話し合った事を、学校に戻っても話しあって欲しい。今日参加の皆さんの次年度以降の協力を期待していると講評がありました。
その後、参加生徒の互選により、12月15日に開催される最終報告会の代表校として以下3校が選出され、発表されました。
・北越高等学校
・長野県松本工業高等学校
・関西学院千里国際高等部
その後、全体写真を撮影して終了しました。改めて リアル開催の良さを感じました。



