開催概要
|
日時: |
2023年11月3日(祝) 13:00-17:00 |
|
場所: |
情報セキュリティ大学院大学東京オフィス |
|
参加人数: |
熟議参加生徒 16人
|
参加校: |
市立札幌旭丘高等学校
|
高校生、教員、企業関係者など72名(YouTube参観除く)の参加者を得て、今、高校生が考えるデジタルシティズンシップとは ―デジタルウェルビーイングな社会を目指して― をテーマに高校生がグループに分かれて活発な議論と発表を行いました。
開会の挨拶
司会進行・主旨説明 実行委員長 米田謙三 様
高校生 ICT Conference の概要及び大まかな流れ、本日のポイントや主旨などを説明しました。サミットの開催にあたり参加者並びに挨拶に参集いただいた共催省庁の皆様に感謝の言葉がありました。
ご来賓挨拶
総務省 情報流通行政局 情報流通振興課長 大澤 健 様
総務省では情報通信・地方自治・行政管理を所管しており、特に情報通信分野では、インターネットやスマートフォンの利用等に係る政策の企画・立案を担当している。その中でも情報流通振興課では、高齢者向けのデジタル機器に関する講習会の実施や、フェイクニュース等に対応するリテラシー向上に関する取組、青少年の安心・安全なインターネット利用の環境整備に関する取組を行っている。本日はこうした取組とも関連する「デジタル・シティズンシップ」をテーマに議論いただくが、各地域におけるこれまでの議論や、本日参集いただいた皆さん一人一人のこれまでの経験を活かして有意義な議論を進めてほしいとご挨拶をいただきました。

こども家庭庁 成育局 安全対策課長 鈴木 達也 様
平成21年に制定された青少年インターネット環境整備法やこれに基づいた基本計画は、危険が潜むインターネットからフィルタリングによりこどもを守るということが基本になっているが、インターネットの活用能力を高めることも定められている。これからは、危険だから使わせないというよりも、こどものうちから、正しく、賢く使うデジタルシティズンシップという方向になっていること、皆さんはこどもの時からインターネットを使いこなしている世代であり、今日は活発に議論を進めてほしいとご挨拶をいただきました。

消費者庁 政策課長 尾原 知明 様
インターネットの発達で、ワンクリックでいろいろなものが買える便利な時代になった。半面新しいサービスが始まるとリスクも生じる。全国の消費生活センターには最近10代ではオンラインゲームや美容、儲け話に関するトラブル、20代では美容、儲け話に関するトラブルが数多く相談されている。これを防止するには皆さん自らがリテラシーを高めることが大切になる。今日のような議論を通じてより良い社会を作っていくことを期待しているとご挨拶いただきました。
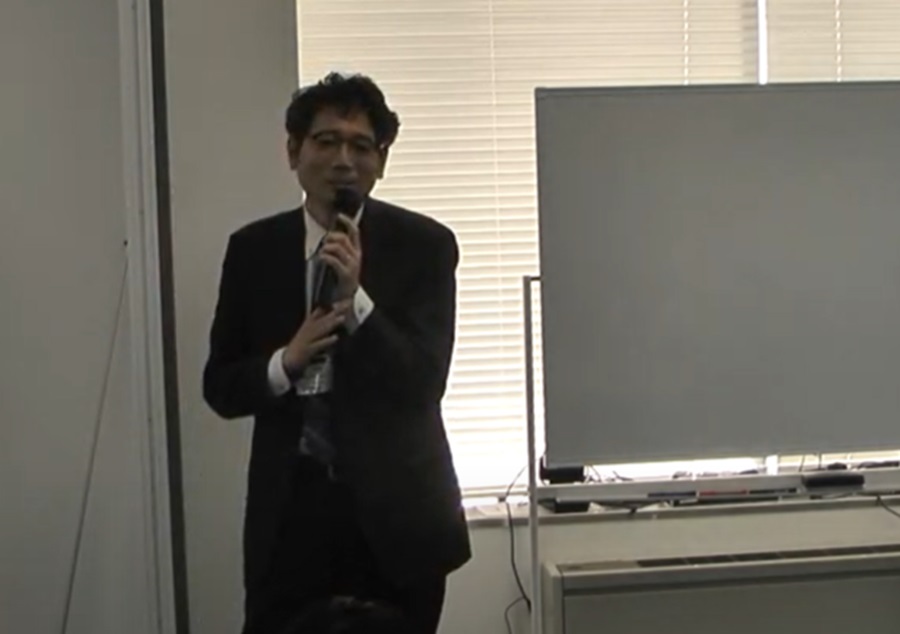
文部科学省 総合教育政策局
男女共同参画共生社会学習・安全課 安全教育推進室長 岩倉 禎尚 様
発展していくICT技術を健全に使うことについて、こうした機会を通じて積極的に議論し、全国に発信して欲しいとご挨拶をいただきました。

警察庁 生活安全局 人身安全・少年課
少年保護対策室長 兼 児童性被害対策官 助川 隆 様
警察庁では犯罪の取り締まりを行うが、SNS関係では事業者と連携して犯罪を未然に防ぐ施策も行っている。例えば同じスマホであっても入っているアプリも使い方も違いがある。そうすると、高校生の皆さんに見えているものが大人には見えてなく、逆もあるはずである。そうしたことを意識し、この機会に周りの大人も巻き込んで議論をして欲しいとご挨拶をいただきました。

経済産業省 商務情報政策局 情報経済課 企画官 橘 均憲 様
生成AIの発展により、私たちの社会は大きな変化に直面している。デジタルシティズンシップとデジタルウェルビーイングは、この変化に対応するために重要な考え。前者はデジタル世界で倫理的に行動することであり、後者はデジタルメディアの利用が自分の幸せや健康に良い影響を与えるように管理すること。最近、若者を中心に、自分のリアルな姿を加工せずに共有するアプリが人気。自己肯定感を高める効果もあるが、個人情報の漏洩などのリスクも伴う。自分の安全や健康を守るために、適切な使い方を心がける必要がある。また、高齢者のICT利用が増えるにつれて、詐欺などの被害も増えている。若い世代が高齢者をサポートすることも大切。今日の議論を地域に広め、みんなで考えていって欲しいとご挨拶をいただきました。

デジタル庁 国民向けサービスグループ 企画官 久芳 全晴 様
「デジタル技術が生活に溶け込んでまだ数十年。皆さんのような若者は便利で有用なものと考えている反面、世代によっては不便なもの・危険なものという印象を持つ方が多い。このようにデジタル技術の利活用の度合いに違いがある中、デジタル庁は「誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化を」目指している。
より良い関係性・社会を作るためには、何かしらのルールは必要になるが、安全が関わる分野は、不安が先行し、規制が厳しくしたいという声が強くなる傾向がある。しかし、デジタル技術を自然に使う若者にとっては、過度な規制となる可能性がある。
そうならないように大切なのは、社会全体のリテラシーを上がっていくこと、そして、それぞれがどのようなルールが望ましいか考え、提案していくことであり、今日の熟議では是非便利さと安全のバランスを考えて欲しい。これから10年20年先の社会を見据えた、世代間の違いを超えた意見を期待している。」とご挨拶いただきました。
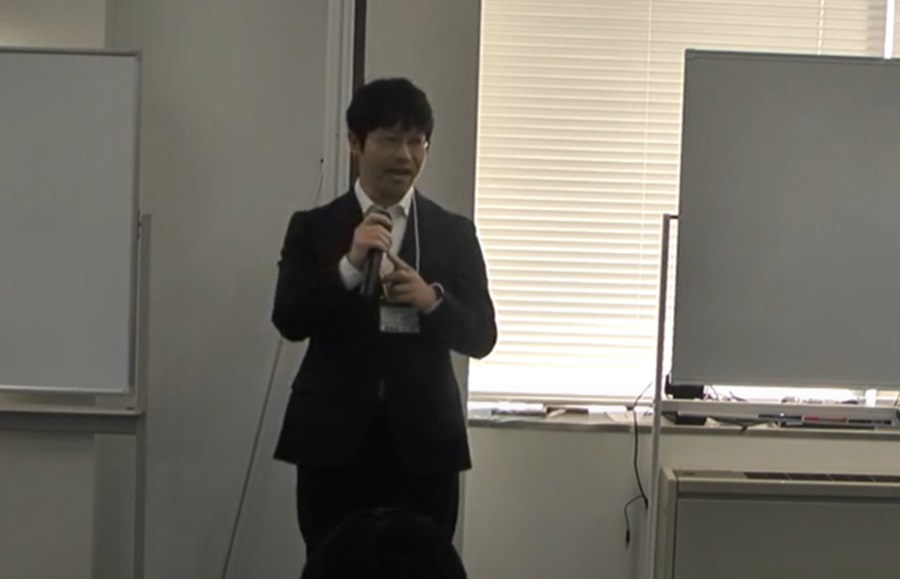
第一部:
各開催地域代表生徒の自己紹介、地域の取り組みの簡単な紹介(各3分)
第二部:熟議
今、高校生が考えるデジタルシティズンシップとは
―デジタルウェルビーイングな社会を目指して―
4つのグループでそれぞれ分かれ最初はファシリテーターの進行のもと、高校生熟議を開始しました。まずは「多様なICT機器の活用と役割」から目的(機能)と利用シーン(機会)から見たICT機器の活用、「安心安全な活用とはなにか」から個人情報、防災、防犯、生成AIなどについてブレインストーミングを実施し、今回のテーマについて 特に 高校生が考える「社会的活用とは(こうすれば快適な社会になる)」「高校生が社会に対して果たせる役割とはなにか」をメインに高校生自身が考える自らの役割、高校生だからこそ果たせる役割(行動、発信、影響力)ということを中心にGoogleスライドを活用しながら意見を整理分類しまとめて行きました。具体的な使い方については、テーマにしぼった班や少し大きなテーマで取り組んだ班などいろいろとありました。熟議の中で分からない事は、省庁の方や先生方にもサポーターとして入っていただき、すばやく答えてくださいました。また今回もファシリテーターはOBOGの大学生・社会人が中心となってくれました。事前にオンラインでのフォームやまとめ方を打ち合わせして、滞りなくまとめることができました。(ファシリテーター研修を今年もほぼ隔週土曜日3か月間にわたって実施しました。
今回の東京サミットの熟議の大切にしたポイント
みなさんが考えるICTの快適な社会的活用と効果はなんですか
1,ICTを活用するとこんなに便利になる
例)入試説明会、入社面接、行政手続、ネット売買、金融手続
2,目的に合った活用で広がる世界
例)学習塾、情報収集(行政情報、地域情報、趣味情報)
3,ICTでつながる外部の世界
例)趣味のブログ、動画配信、オンラインセミナー
4,不利な条件を乗り越える
例)時間、距離、移動手段
5,ICTの新しい活用法
例)効率的学習、文章作成、翻訳、会話型検索
高校生が社会に果たせる役割とは何か ―行動、発信、影響力―
1,ICTの活用を届けたい世代は?
幼児、小中学生、大人、高齢者 ・・・
2,ICT活用の先頭を走る高校生から見た活用法
生活の一部としてのICT
3,どうしたら全世代が使えるようになるのか
機能、ソフト、サポート、アシスト・・・
4,新しいAIとの付き合い方
活用方法を創造する
5,今高校生が果たせる役割
家庭で、社会で・・・・
第三部:グループ発表
各グループともプレゼンテーションソフト(Googleスライド)を活用して4分の発表を行いました。(詳細は別紙「グループ発表資料」をご参照ください)
リアル熟議・発表でどのグループもその分内容が充実していて本当に提言としてよくまとまった発表となりました。劇を入れたグループやすぐにできる提言もたくさんありました。
講評で米田実行委員長 がまとめた各班のポイント 参考 発表順
【4班】 My Candy Plan ~世代をくるりんちょ~
様々な世代に高校生が情報を発信
ICTに慣れているため自分たちで情報を発信できる
提言
小中生 : ゲームを使って一緒に学ぶ
→リテラシーに関するゲームの紹介・体験
上の世代: デジタルを受け入れてもらう
→小中学生に向けた取り組みの様子を親世代に
行政 : 過疎地域や自分たちが できないところを補ってもらう
→人を呼び込みサイクルを生み出す
高校生があらゆる世代を巻き込む 学校用ポータルアプリの制作
【3班】 「教育」 現在の環境から分かる「教育」への問題点と解決策
変化の激しいICT技術社会の 最前線に立つ高校生
教育「される」側と「する」側
高校生は大人から教育 →リテラシー・ICT教育
小中・高齢者に教育→スマホ使い方・自分の活用
行政への提言 より自由な探求・調査 グループワーク・最新の環境対応
BYOD端末の改善 ➡スペック・Wi-Fi・一括管理
ICT教育の改善・追加➡GIGAスクール構想改善
高校生へ ICTの知識を率先して広める
文化に「従う」 → 文化を「つくる」 側へ
【2班】 小中学生のデジタル教育 TARGET:義務教育
1)デジタル機器に関する開放性を高める
学校でのスマートフォン等の利用を認める
2)小中学生に実践的なICTの使い方をカリキュラム
日常生活でICT機器を使う年齢が下がっている
デジタルシティズンシップとは →適応力
・多角的な視点で客観的に判断できる力
→より実社会に近い環境で実践して学ぶ
デジタルウェルビーイングな社会に
【1班】 快適に使うためには土台の充実!
高速ネットワークなどの インフラ整備 Well-being!
ネット環境もインフラの時代に だれひとり”取り残さない”
SNSアプリ「ウェルシプ」 ←ICTの役割
1)現代版避難訓練 加害者と被害者両方の立場でディジタル体験
2)地域の魅力発信 若者のU・J・Iターン! 高齢者へのICT教育の足がかり
3)コミュニティ設定 より良い社会に (家族/学校/会社/町内会ディジタル化)
4)モチベーション・マネジメント
生成AIを用いて好きな人(推しなど) モチベーションのマネージャーに
ライフワークバランス (学習/生活習慣/スマホの使い過ぎ)
→これらをマネジメント
「運営方法」 高校生主体 安全安心のために マイナンバーとの紐づけ
→ 一人一アカウントを基本とし
なりすまし・誹謗中傷を許さない仕組み 海外等へ
講評:大阪私学教育情報化研究会 副会長 米田謙三 様
今回も大学生・社会人のファシリテーターのもと本当にいろいろな意見がここまで出てきて大変良かったと思います。今年は愛知の復活、兵庫からの参加校も増えました。デジタル庁様の共催も増えました。来年もさらに盛り上げていってほしいと思います。また 今回話し合った事を、学校に戻っても話しあってほしい。次年度以降もいろいろと協力してほしいと思い講評をいただきました。
その後、参加生徒の互選により、12月1に開催される最終報告会に行くグループでの代表者が選出され、全体会で発表されました。
・長野県松本県ケ丘高等学校
・長崎県立壱岐高等学校
最後に全体写真を撮影して、今年もリアル開催の良さを感じました。



